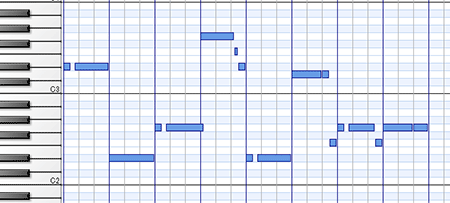曲のキーを調べて打ち込みを楽にする
最近の音楽のほとんどにはキーとスケールがあります。
(調性音楽)
このキーとスケールを特定すれば、耳コピはずいぶんと楽になります。
スケールの構成音から外れた音はあまり使われないからです。
イントロのドラムとベースが出来たら、打ち込んだベースラインを見てみましょう。
特に長く延ばされている音に注目します。
一小節ごとに、
- E♭
- E♭
- G
- G
- E♭
- D
- G
- G
という音になっています。
この曲のコード進行は割と簡単な方なので、慣れた人なら聞いただけで大体キーは特定できます。
「終始感」のある音に注目する
楽曲は一般的に「イントロ」「Aメロ」「サビ」などのいくつかのパートに分ける事ができます。
それぞれのパートの中で、小節の最後の音に終始感を感じるパートがあります。
絶対ではありませんが、J-Popでは多くの曲にあります。
この曲の場合は「イントロ」「Aメロ」「Bメロ」「サビ」「間奏」というパートで構成されています。
そしてBメロ以外はすべて同じ音で終了していて、それぞれのパートの最後の音に「安定感」「終始感」があります。
今打ち込みしたイントロのベースを再生して、最後の音に終始感がある事を確認してください。
この終始感を感じる音が曲のキーとなっていることが多いのです。
この曲の場合、最後の(終始感を感じる)音は「G(ソ)」になっています。
Gといってもメジャースケールとマイナースケールがあります。
メジャーは明るい曲、マイナーは暗い曲と言われますが、この曲は暗いというか物哀しい雰囲気があります。
なんとなくマイナーな感じがしますね。
Gメジャースケールの構成音は
- G(ソ)
- A(ラ)
- B(シ)
- C(ド)
- D(レ)
- E(ミ)
- F♯(ファ♯)
になります。
次にGマイナースケールの構成音は
- G(ソ)
- A(ラ)
- B♭(シ♭)
- C(ド)
- D(レ)
- E♭(ミ♭)
- F(ファ)
になります。
スケールの構成音が分からない場合は、Gから順に「全全半全全全半」と音程をたどってください。
それがGメジャースケールの構成音になります。
マイナースケールの場合は「全半全全半全全」です。
このあたりの事は五章 コード入門で説明してます。
すでに打ち込んだベースの音と比べてみると、GメジャースケールだとEの音が合いませんね。
Gマイナースケールだと構成音に矛盾はありません。
どうやらこの曲はGマイナーで良さそうです。
まだ耳コピした音数が少ないのでこれで断定はできませんが、とりあえずはGマイナーであると仮定して続きを打ち込んでいくことにします。
早めに曲のキーを確定させる
複雑な曲でない限りほぼGマイナーと決定としてしまっていいのですが、もう少し打ち込みしてみて矛盾がないかどうかを調べておきましょう。
この曲のAメロに当たる部分のメロディラインを打ち込んでみましょう。
音色はとりあえずピアノでも何でも構いません。
(クリックで拡大します)
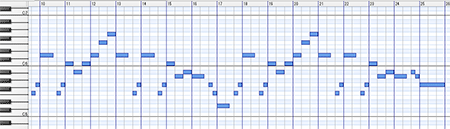
さてメロディに含まれる音程を書きだしていくと、
- D(レ)
- F(ファ)
- G(ソ)
- A(ラ)
- B♭(シ♭)
- C(ド)
となります。
これに先ほどのベースの構成音を加えて順番を整理してみると、
- G(ソ)
- A(ラ)
- B♭(シ♭)
- C(ド)
- D(レ)
- E♭(ミ♭)
- F(ファ)
Gマイナースケールの構成音と比べてみると、
- G(ソ)
- A(ラ)
- B♭(シ♭)
- C(ド)
- D(レ)
- E♭(ミ♭)
- F(ファ)
どうやらピタリと一致するようです。
これはGマイナーで確定してしまっていいでしょう。
構成音を基本として音を探っていく
このように、まずは比較的聞き取りやすい音を耳コピしていって曲のキーとスケールを確定しておきます。
基本的なコードを使っている限りはスケールの構成音から外れた音程はあまり使いませんから、聞き取りにくい楽器の音をコピーするときにある程度推測できるようになります。
ただし、使用するコードによっては上記の構成音以外の音が入ることもあります。
この曲でも構成音以外の音が入るコードを使用する場面があります。
また、この曲にはありませんが、転調のある曲ではキーやスケール自体が変わるのでその度にキーを調べなおす必要があります。
曲によっては終始感をあまり感じない場合もあります。
その場合はとにかく聞き取れる音程を全部書きだしてしまって、それからキーを類推します。
ちなみに、シャープやフラットが付かない曲はCメジャースケールかAマイナースケールです。
シャープは「ファドソレラミシ」の順番に付くと決められています。
フラットは「シミラレソドファ」の順番に付くと決められています。
(ファドソレラミシの順序を逆にしたもの)
「ファドソレラミシ」「シミラレソドファ」と何度も発声し、覚えてしまうとちょっと便利になります。
そしてシャープがひとつ付くごとに「現在の音から上に5度の音がキーになる」という法則があります。
(現在の音を1度と数える)
Cメジャーにシャープがひとつ付くと、上に5度の音であるGメジャーになります。
反対に、フラットがひとつ付くごとに「現在の音から下に5度の音」がキーになります。
Cメジャーにフラットがひとつ付くと、下に5度の音であるFメジャーになります。
この曲の場合、フラットが2つだからB♭メジャーかGマイナーかのどちらかになる、ということが分かります。
終始感のある音がGなのでGマイナーである、と特定できます。
この辺のことはコード入門後半 - キーの変更で説明しているので、よければ目を通しておいてください。
(わからなくても耳コピやキーの特定はできます)