主要三和音が主要な理由
さて前ページの内容は、ある程度理解できたでしょうか?
理解できたなら、コードの基本は大丈夫です。
キー(DメジャースケールとかEメジャースケールとか)が変わった場合に少しややこしいかもしれませんが、基本となる音から「全全半全全全半」とたどっていけばスケールの構成音は分かります。
そこから一音飛ばして音符を重ねていけばそのスケールのすべてのダイアトニックコードが作れます。
「1、4、5」番目のコードが主要三和音になるのですが、なぜ主要なのか、どういう役割があるのかを説明します。
コードにはそれぞれ機能、役割があります。
あるコードは安心感を与え、あるコードは不安や緊張感を与える…といった具合です。
それらを組み合わせることで曲に展開が生まれます。
以下の図を見てください。
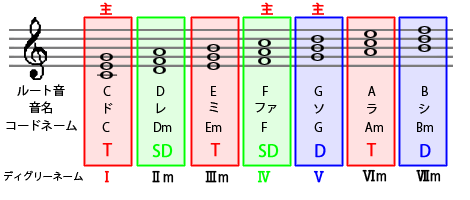
全ページで登場したCダイアトニックコードを機能別に色分けしたものです。
コードの機能には「トニック」「サブドミナント」「ドミナント」の3つがあります。
- トニック(T)
-
強い安定感を持つコード。
曲の最初のコード、また終止コードとしてよく用いられる。
最も基本的なコードで、ここからトニック、サブドミナント、ドミナントのどのコードへもスムーズに進行できる。 - サブドミナント(SD)
-
トニックとドミナントの中間的な性格のコード。
進行に彩りや発展的な印象を加える。
割と中途半端な性格で、トニック、ドミナントへ進行できる。 - ドミナント(D)
-
不安定感を持つコード。
主要三和音の中では一番緊張感のある音。
不安定なので、安定を求めてトニックへ移りたがる性格を持つ。
これらは絶対ではなくて、例えばドミナントはトニック以外には進行してはいけないということではありません。
図中で上に「主」と書かれているコードは、それぞれの役割を持つコードのうちで代表的なものです。
主要三和音である「1、4、5」番目と同じですね。
それぞれの役割をもつコードの中で、最もその性格がはっきりとしているもの、いわば代表選手が主要三和音と呼ばれているというわけです。
Cメジャースケールの場合は
- 1番目の「C(Cメジャー)」がトニック(の代表)
- 4番目の「F(Fメジャー)」がサブドミナント(の代表)
- 5番目の「G(Gメジャー)」がドミナント(の代表)
となります。
代表選手に選ばれなかったコードは、代理コードとして主要三和音の代わりとして使用されます。
ちなみに、三番目の音(III)は上図ではトニックに分類していますが、ドミナントの役割を担うこともできます。
主要三和音の役割の確認
主要三和音があればコードの役割は一通りそろうので、曲は作れます。
主要三和音だけを使ったサンプル曲を作ってみました。
■主要三和音
このサンプル曲のコード進行です。
黒字はコードネーム、赤字のTはトニック、SDはサブドミナント、Dはドミナントを表します。
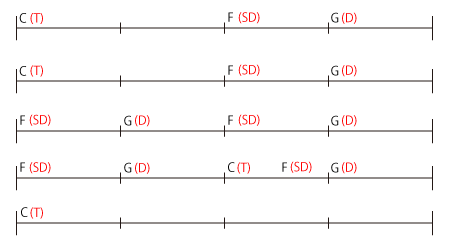
まずCから始まり、安定感のある響きが2小節続きます。
Fに移ると、「曲が展開した」と感じられると思います。
Gでさらに曲が展開し、Gはドミナントなのでトニックに行きたがります。
期待通り2段目の最初でトニック(C)に進みます。
1段目と同じ進行を繰り返し、 2段目最後のGでまたトニックに進行したくなります。
しかし3段目ではサブドミナント(F)に進行し、期待を裏切ります。
そしてF→Gが繰り返され、安定しない響きが続きます。
不安定な感じが続くと、聞き手は安定の出現を期待します。
4段目後半でトニック(C)が出現し、ようやく安定したかと思ったらまたすぐにFに進行し、期待を裏切ります。
しかし聞き手は繰り返しだった曲に変化が起きたことで新たな展開を予想します。
最後に長く続いた不安定感の帰結としてトニック(C)へ進行し、強い安定感、終止感を出して曲は終了します。
・
・
・
と、文字で説明すればこんな感じになるんですが、普通聞き手はいちいちこんな小難しいことは考えません。
しかし無意識のうちに曲の流れは感じ取っています。
流れが素直過ぎると退屈な曲と感じてしまうため、所々で「予想通りにはいかせない」ことで曲に変化が生じ、面白みが増します。
コードの役割を説明するためにさんざん変化とか期待を裏切るとか言いましたが、この曲程度のコード進行なんて聞き手は十分予想の範囲内だとは思います。
ここではあまり難しいことは扱いませんが、副三和音やさらに複雑なコードを使って聞き手を飽きさせない進行を作るのがコードアレンジです。
とはいえ、無茶苦茶な進行などであまりに期待を裏切りすぎると聞き手はついていけなくなるので注意しましょう。
今はコードの機能を理解して、主要三和音だけで簡単なコード進行を作れるようになりましょう。
コードの役割まとめ
- コードにはそれぞれにトニック、サブドミナント、ドミナントという機能・役割がある
- 主要三和音は各役割からの代表選手
- コードの機能を素直に使うかどうかはアレンジ次第
- 聞き手が無意識的にする予想を裏切ることで単調さをなくす