エクスプレッションで演奏に抑揚を
ストリングスやトランペットなどの音を長く持続させるとき、抑揚(音量の上下)がないと平坦で機械的に聞こえてしまう事があります。
また曲の展開に合わせて大音量で盛り上げたり蚊の鳴くような弱々しい音を奏でたりと、抑揚は雰囲気作りにも重要な役割を持ちます。
このような演奏の抑揚、音量の時間的変化はエクスプレッションというコントロールで設定します。
■エクスプレッションの例
メロディ(トランペット)の最初の音に注目してください。
最初は強く、急に小さくなり、次第に大きくなっていくという変化がわかると思います。
| メッセージ | 設定値 | 説明 |
|---|---|---|
| CC11 | 0~127 | エクスプレッション(抑揚)を設定する |
エクスプレッションは擦弦楽器(バイオリンとか)や管楽器、アコーディオンなどでは常に変化するパラメーターです。
つまり生演奏をシミュレートしようとするならば、すべてのノート情報に対してエクスプレッションを書いていく必要があります。
こだわるなら打ち込みがなかなか面倒くさい部類になります。
ほかには音の立ち上がり部分はエクスプレッションをほぼゼロにしてアタック音を削るなど、エンベロープジェネレータ的な使い方もされます。
ついでにもう一つ関連するコントロールを説明します。
| メッセージ | 設定値 | 説明 |
|---|---|---|
| CC7 | 0~127 | 音量を設定する |
エクスプレッションとボリュームは似た働きをします。
実際に、いくつかの音源では両方のコントロールを入れ替えても結果は同じになります。
ボリュームとエクスプレッションの関係は後述します。
GM音源対応ではないソフトシンセの場合、エクスプレッションメッセージに対応していないことがあります。
その場合はボリュームメッセージで抑揚をコントロールします。
ソフトシンセの場合は音源本体から出力された音はさらにDAW上のミキサーで音量コントロールが可能ですので、ボリュームメッセージを擬似的にエクスプレッションのように使う事ができます。
ボリューム・エクスプレッション・ベロシティの関係
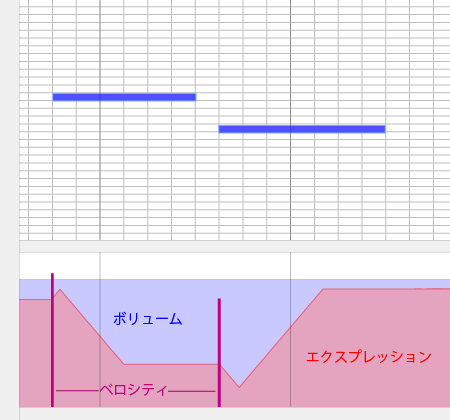
主に音量に関係するコントロールには
- ボリューム(CC7)
- エクスプレッション(CC11)
- ベロシティ(ノート固有の情報)
の3つがあります。
それぞれ意味や聞こえ方が異なりますので正しく使い分けしましょう。
ボリュームは各チャンネルごとのメインとなる音量を設定します。
これは曲頭で設定した後は基本的に変更せず、フェードイン/フェードアウトなどの音量コントロールが必要な場面で使用します。
AメロとBメロで音量を変更する場合など、楽曲の構成に合わせて音量を変化させる場合もボリュームを使用します。
ペロシティとエクスプレッションは演奏の抑揚を表現します。
ベロシティは楽器を叩いたり弾いたりする強さをコントロールします。
ピアノやドラム、ギターなどの減衰系の音色、つまり打楽器や撥弦楽器のコントロールに向いています。
エクスプレッションは楽器の音を出した後の音量をコントロールします。
フルートやストリングスなどの持続系の音色の抑揚表現に使用します。
ボリュームとエクスプレッションは音源によっては同じ変化となりますが、いくつかの音源ではエクスプレッションで変化させた場合に音色が変化する物もあります。
それぞれの違いは難しいものではありませんが、音源が対応しているのなら抑揚表現は素直にエクスプレッションを用いましょう。
Dominoでのコントロールチェンジの打ち込み方
ベロシティの時の説明と同じになるかもしれませんが一応Dominoでのコントロールチェンジの打ち込み方を説明しておきます。
※注意
音源定義ファイルの設定をしていないと「Expression」などの各項目が表示されません。
使用する音源の音源定義ファイルがない場合は「GM Level1」を設定しておいてください。
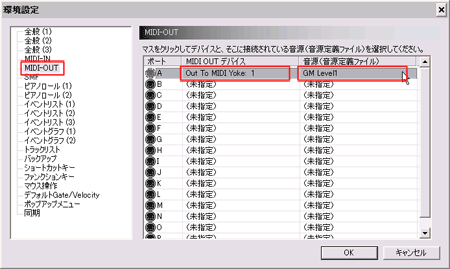
■Dominoでのコントロールチェンジの打ち込み
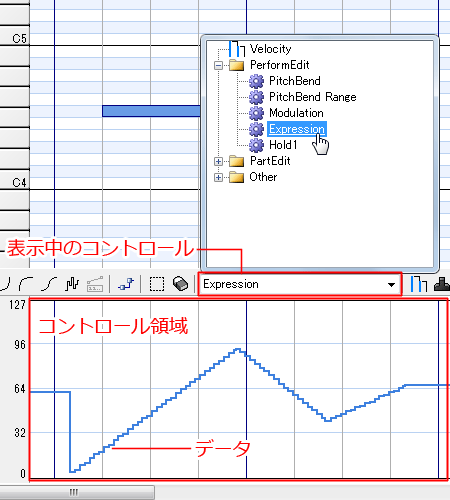
ベロシティの時との違い、折れ線グラフを書いていくようなコントロール方法となります。
これにより発音の途中からだんだんとエクスプレッションを大きくしていくというようなコントロールが可能になります。